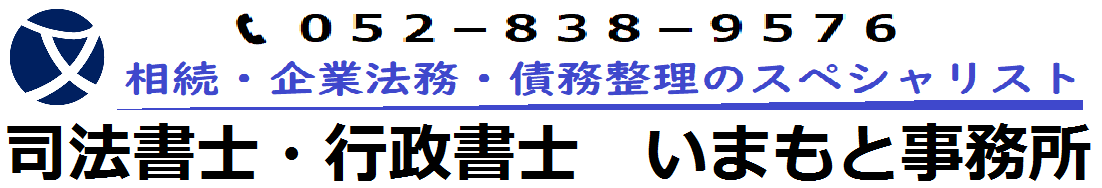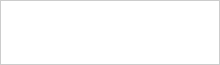不動産決済中心の事務所にいて若干2年勤務した経験から、不動産決済にのぞむ上での致命的な落とし穴を振り返ろうと思います。
司法書士事務所勤務は、その事務所によっては新人に対してやや放置寄りの対応をされることもあろうかと思うので、勤務されて間もない方は不動産決済の「地雷」に注意して業務に励みましょう。
なお、ここで言う「不動産決済業務」とは、当日の出席だけではなく依頼対応、見積り、書類作成、本人確認、申請、完了後の郵送までを含みます。
見積り
見積書を作成するうえで「登録免許税」の計算は必須です。
シンプルに税率計算すれば良いと考えられますが、落とし穴があります。
そもそも計算の基礎となる不動産評価額が問題なのです。
評価地目が適正か

不動産評価額を見るにあたり、評価額は現況(課税)地目をベースとしています。
そして評価証明書はその年度の1月1日の時点での状態を4月1日に発行しています。
では、評価証明書上現況が「畑」の土地が売買に伴い農地転用、2月1日に宅地造成を行った場合はどうなるでしょうか?
そう、「畑」の評価ではなくなります。
この場合は基本的には近傍評価(状況が類似する周辺の土地評価)を基に計算するのが通常です。
地積更正の発生
不動産の面積が変わることがあります。
登記上の面積が「110.00㎡」なのに対し評価証明上の現況面積が「105.00㎡」である場合は現況評価の㎡単価をベースに登記上の面積を乗じて計算する必要があります。
これも1月1日以降に「地積更正」を行なったことで変わっていることがあります。
特に不動産会社が「仕入れ」として土地購入をする場合は引渡し前に測量を行う事が多く、測量結果により面積が一定の公差以上であれば地積更正登記を行います。
決済直前に登記記録を閲覧したらいきなり面積が違った、なんていうこともあるので注意しましょう。
生産緑地指定
土地の評価が極端に安い場合は注意が必要です。
その土地が評価時点で「生産緑地指定」を受けている可能性があるからです。
この場合も評価地目の項目で説明したような近傍評価に基づいて計算するのが通常です。
「なんでここはこんなに安いのだろう?」と思ったらいったんこの点に注意してみましょう。
住宅用家屋証明書など減税適用
司法書士試験受験生のころはこんな勉強していないと思いますが、租税特別措置法により減税適用がある不動産売買が多いです。
例えば土地の売買による所有権移転の登録免許税率は令和7年8月27日現在、(令和8年3月31日までの間)20/1000ではなく15/1000となります。
建物においては住宅用家屋証明書を添付する形での中古や新築の所有権保存、移転で更に安くなっております。
この減税の適用があるか無いか、それで税額が大きく異なるので、お見積もりの際には注意が必要です。
いろいろ論点はありますが、大きな地雷は以上の点です。
見積りは安くなる分にはいいのですが高くなった場合にお客様からのクレームになりやすいので特に注意が必要です。
次回は書類作成の項となります。