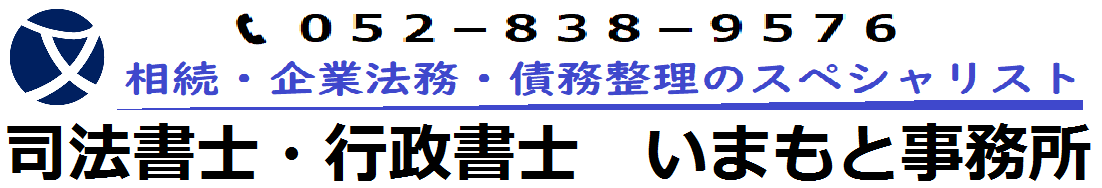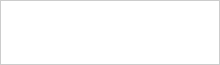試験合格者や事務所勤務者は「まず独立で食べていけるか」想像することがあると思います。
筆者も例外ではなくそのあたりがすごく気になっていろいろなネット記事を見ていました。
実際に開業した立場として、ここでは資格関係の業者が書けないような、可能な限りリアルで具体的な内容を書きたいと思います。
初期費用
まず最初の費用が気になる方が多いと思います。
登録費用
あまり覚えていませんが、30万円くらいかかったような気がします。
これは事務所によっては「ウチで勤務したら登録費用出すよ」というところもあるので、こう言ってはなんですが、一度どこかそういうところで勤務された方が金銭的にも実務経験的にも良いかと思います。
研修費用
新人研修、ブロック研修、配属研修があります。
また、簡裁代理権を得たい場合は特別研修もあります。
筆者は実は配属研修は受けていません。
新人研修とブロック研修は必須で、こちらは筆者も受けており、数万円程度かかったように思います。
この点も登録費用と同じで出してくれる事務所を探す余地があるので、一度勤務された方が無難かと思います。
特別研修は14万円くらいだったでしょうか。
費用もさることながら拘束時間もなかなか長いので、どこかで働きながらであれば勤務先の協力が必要かもしれません。
あと当時は土日がほぼ潰れました・・。
特別研修と簡裁代理権ですが、「あんまり仕事で使わないから受けない」みたいな方が時々いらっしゃいます。
私個人としては「受けない選択は無い」と言っておきます。
理由ですが、例えば他資格で「行政書士」や「土地家屋調査士」を取得してダブルないしトリプルライセンスで業務を広くカバーすると必ず「会費」がかかります。
こういったランニングコストが無いのが簡裁代理権です。
取得しても会費が変わらないで業務出来る権利が増えるので何も損はしません。
また、お客様からの相談に応じられる範囲が全然違います。
特に司法書士を「法律家」として法律上のトラブルなどの相談をしに来られる方がおり、それを弁護士法違反にならず対応できるのは大きなメリットです。
そして何もそういった訴訟関係だけではなく、相談をきっかけに別業務を依頼されることもあります。
また、所属する会や支部の相談会参加要件で簡裁代理権を要する場合があり、これを満たさないとそういった機会が失われます。
これから取得を考えている方はぜひ認定考査の合格を目指しましょう。
自宅開業と事務所賃貸
筆者は事務所を借りました。
初期費用は30万円くらいだったでしょうか、多分これは安い方です。
都合よく適度な広さと立地、家賃である物件が見つけられるものではありませんし、高い場合は3ケタ万円の初期費用がかかる物件もあります。
郊外になると「無駄に広くて無駄に高い」物件が多いように思います。
一方自宅開業はそういった憂いはありませんが、その人の居住環境、広さ、部屋割り、構造によって事務所を運営するに適したものかどうかという点があります。
正直な感想、仕事さえ取れれば自宅開業で良いのではないかと思いますが、筆者は事務所構えたからこそ得られた継続的な仕事もあるので、こればかりは個人の判断に委ねられます。
備品や什器
事務所の広さによります。
買おうと思えばパーテーションや机、椅子、カウンター、本棚などキリがありませんが、
最低限プリンタ―とパソコンは必要です。
これは何をどこまで求めるかなので何とも言えませんが、少なくともofficeソフトが普通に動かせる環境でありたいものです。
プリンタ―は通常のレーザーまたはインクジェットのもののほか、「ドットプリンター」というものがあります。
これは銀行から抵当権の書類を預かって、そこに「打刻」するような形で印字するプリンタ―です。
複写式の書類の物件情報を印字するのに適しており、これが14万円くらいしてけっこうな値段でした。
プリンタ―もパソコンも結局は何をどこまで求めるかなので、不便が生じたら別のものを買う感覚で良いかも知れません。
また、地味な話ですが、オンライン申請用の電子署名取得で数万円払うことに留意しましょう。
自動車
多くの地域の業務で自動車が必要です。
自家用車を兼用する形が楽でしょうか。
雨風しのげて田舎にも移動できる自動車は必需品だと筆者は思います。
乗れれば安くても良いと思います。
ランニングコスト
- 水道光熱費
- ガソリン代交通費
- 通信費
- 司法書士会費(筆者の地域は毎月19000円の3か月ごと支払い)
- コピー紙や文房具などの消耗品
- 交際費
- 事務所家賃と駐車場代
主にこんなところでしょうか。
交際費や事務所家賃、駐車場代なんかは環境や方針によってはかからないと思います。
自宅開業でやれば10万円もかからないんじゃないかと思っています。(どれくらい家事と経費按分するのか次第ですが)
売上
コストのお話が終わったので次は売上です。
食べて行けるかどうか不安な方はこの「売上」が想像できないのが理由だと思います。
まずはランニングコストの試算に応じて売り上げ目標を立てましょう。

例えば、ランニングコスト15万円だとして売上は50万円くらいは欲しいです。
なぜならこの差額の35万円そのままもらえる訳ではなく、そこに所得税や個人事業税の課税もあります。
社会保険料も合わせると、手元に残るのはそんなに多くはありません。
おおよそでいいので、この「売上目標」を立てるのが重要です。
そうしないと今自分が「足りてる」のか「どれくらい足りてない」のかわからないからです。
この売上目標に対し「客単価」を想定して、例えば「相続ならこれくらいだな」「法人登記はこれくらいか」として、何の案件を何件受けられるように営業するか決めましょう。
それ次第でどういった層をターゲットにして営業するか方針決定します。
コネが無くても大丈夫なの?
よくこの点について不安な方がいらっしゃいます。
よくよく考えてみてください。
仮に1社、2社程度の「コネ」があったとして、その会社には月に安定してどれくらいの仕事を発注していただけるのでしょうか?
断言しますが、ちょっとやそっとのコネなんてあっても無くても変わらないので、普通に営業努力をしましょう。
筆者はコネなんてありませんでしたが、開業後に知り合ったいろいろな方にお世話になっております。
そういった方々には「コネ」だとか「人脈」という言葉は使いたくありません。
人としてお世話になっている、大切な方々であると思います。
どうやって受注するの?
筆者がやったことは
- ホームページ自作
- チラシ配布
- フリーペーパー掲載
- ポータルサイト掲載
- いろいろな団体に参加
- テレアポ祭り
- 直接訪問祭り
このあたりでしょうか。
以下、効果について書きます。
なお、どの方法が刺さるかは地域性やブランディングなど環境要因や事務所特性が大きいので、筆者にとって効果的であったものがイマイチだったり、その逆もあったりすることをご留意ください。
ホームページ
ワードプレスで自作だったので、そのための書籍代しかかかっていません。
初見で一般のお客様の導入はホームページからが多いのでこれは絶対に作った方がいいです。
SEO対策とか難しいと考えると思いますが、経験則でお客様は「近くの事務所に行く」傾向があるので、グーグルマップに載ってさえいればそこからお問い合わせいただけると思います。
したがって、ホームページとセットでマップ掲載は必須だと思います。
チラシ配布
効果はゼロではないですが、薄かったです。
後述するフリーペーパーの方が効果ありました。
フリーペーパー
効果ありました。
1回4万円程度の掲載料であれば基本的には1回の受注があれば良いのです。
しかしこれは「何のフリーペーパーに載せるか」が重要で、その発行部数や陳列場所、配布の有無など様々な要素があります。
とりあえず1回掲載してみてのトライアンドエラーで調査しても良いかも知れません。
チラシとの大きな違いは「一定期間お家に置いてもらえること」です。
一過性ではないので、一度の広告で数度目を通してもらえる可能性があります。
ポータルサイト掲載
これもフリーペーパーと同じく何に載せるか次第です。
また、ポータルサイトそのもののSEOが重要で、順位が低いと載せる価値はありません。
SEOの順位は日々変わっており、掲載当初は良かったけど後からダメになった、そういうこともあるので、フリーペーパーよりもタイミングが重要となります。
いろいろな団体に参加
これは団体による差が著しいです。
異業種交流会みたいなのは結局ダメなんだと痛感しました。
環境にもよりますが、地域性の強い団体がしっかりとした関係を築けると思います。
まず、「普通の人間関係」を築くのが最重要で、営業だなんだという色で接しない方が良いです。
我々の仕事は、その必要があるときに「ああ、あの人がいたね」と思い出してもらえる程度で良く、それまでに普通に仲良く親交を深めるだけで良いのです。
そこで仕事が来なくてもいいや、そんな気持ちが大切です。
ところが異業種交流会は大体が「仕事とってやる」みたいな人ばかりで(偏見かも知れませんが)、かつ、地に足がついてない方も散見され、結局はネットワークビジネス(マルチ商法)の勧誘に遭って終わり、そういうパターンが多かったです。
自分を大きく見せようとする人も多く、興味本位で参加するならともかく過度な期待はできない場であることを踏まえた方が良いと思います。
そこでは「人脈」という言葉が大好きな方が多いです。
テレアポ祭り
関係する業種の営業所をエクセルで3ケタに及ぶ数をリストアップ、電話しました。
命中率は著しく低いですが、結果だけ見れば多大な効果がありました。
まさに数うちゃ当たる、です。
電話のほか、お問い合わせメールからというパターンもあります。
みっともない真似だと思う方もいらっしゃるとは思いますが、やることやらないでダメだった、は言い訳にならないので筆者は実施しました。
直接訪問祭り
命中率ゼロ。
だめでしたね。
何というか、根性がやたら養われたと思います(笑)。
ここまで来るとやることやった感はあります。
結局のところ食べていけるのか
どこまでを求めるかで異なります。
1人で暮らすだけなのか、家族を養うのか。
おおよそ2~3割が経費と考えて検討します。
売上20万円で利益14万円
この水準は永続的に生きていくのが楽とは言えません。
しかし、開業当初はコンパクト経営で「とりあえず」これくらいを目標にして、「持続力」を確保した上でより良い目標達成を目指すと良いと思います。
この売上ですと不動産決済1.5件または相続登記2件前後で達成可能だと思います。
そう考えるとハードルは下がりますが、経費の観点から広告費と「何の方法で広告するか」がテーマになります。
ちなみに筆者の最低月額売上はこれより全然低かったです・・。
売上40万円で利益28万円
これを永続的に達成できるととりあえずは「普通に生活できるかな」という印象になります。
しかし、受注の性質上上下動があるので、実際の売り上げは20万円~60万円で推移することも多く、下がった時のメンタルはかなり病みます。
資産に余裕がある人を除き、精神安定剤は預金残高と売上高、そうなると思います。
受注内容としては不動産決済2件と相続登記2件、追加で法人登記も少しあれば達成可能かと思います。
やはり不動産決済の有無は売り上げへの影響として大きく、ここを受注しない場合は相続に力を入れるか債務整理や法人登記、行政書士を保有している方は許認可を受注するなどして売り上げをフォローしていく必要があります。
売上100万円で利益74万円
家族を養う方はこのあたりを達成したくなります。
利益が74万円だとしても各種税金と保険料の負担でそこまで裕福ではありませんが、一定の安心感はあります。
更にこれ以上多くを求めると従業員が必要だとか業務効率を上げるだとかそういった観点が求められるように思えます。
受注内容は事務所によって異なりますが、大きく分けて
- 業務特化型
- 守備範囲型
- 大きい取引先確保型
大まかにはこの3つに分かれているように感じます。
「業務特化型」は、例えば外国人関連の渉外業務や家族信託など、一定の高単価業務を得意分野としてブランディング、受注するスタイルです。
「この分野ならあの人にお願いするしかない」「あの人が多分詳しい」そう評価されることは大きいです。
とはいえこれだけを業務としている訳ではなく他の業務も受注しているのですが、「主砲がある」というのはやはり強いです。
特に外国人関連の業務は今後増加が見込まれるので、ブランディングするかどうかはともかく受け皿としての準備はしておくに越したことはないと思います。
個人的には「土地家屋調査士併用型事務所」のような形式は、これにあたるような気がします。
不動産登記のスペシャリストとして測量、合分筆、表題登記を経て所有権や抵当権の登記を行うメリットは多大で、渉外分野に比べてその事務所の供給数が多いにも関わらず住宅関連業者の方から重宝される関係から、後述する「大きい取引先確保型」に移行しやすいタイプと言えます。
「守備範囲型」は器用に何でも受注するスタイルです。
「ウチはそれやってないんだよね」をゼロ、もしくは極力少なくする方針になります。
開業当初はこのような傾向になりがちで、筆者もいまだにこの部類に入ります。
実務未経験者の方にとっては意外かもしれませんが、「ウチは決済とか受けませんし不動産屋とは付き合いません」「商業登記とか苦手でやったことないから避けてる」「債務整理は難しそうだから手を出せない」そういう司法書士は少なくないので、そこの受け皿になる形で受注します。
資格があれば行政書士業務も受けます。
弱点としては事務所自体をブランディングしづらいところで、あくまで個人である「自分自身」を売り込む傾向にあるところです。
「大きい取引先確保型」は、大手決済事務所のような、多くの件数を受注する事務所です。
また、個人の事務所でも大きな取引先を何件か確保している方もいらっしゃいます。
こればかりは「ご縁」や「機会」が無いと構築できないので、基本的には他のスタイルで始めつつこのスタイルに至るのが王道かと思われます。
いきなりホームランを打ってこのスタイルに至るのは極めて難しく、多くは「長い勤務中に仲良くなった会社と懇意に」「土地家屋調査士も含む合同事務所で多くの業務を行っている実績から」「普通に長くやっているうちに受注が来て」のような前提事実を基にこのスタイルに至るような気がします。
まとめ
「食べていけるか」の結論としては「どこまでを求めるか次第」だと思います。
求める目標に対して得意不得意の自己分析を経て戦略を考えるのが通常ではないでしょうか。
司法書士登録したてのいわゆる「スタート」周辺の状態の方は、そこの時点で勝敗を決するような、独立にとって都合の良い「下駄」はそう滅多に無いもので、結局はゴールに対して現時点からどのような働きかけを行うか、行い続けるかだと思います。
追記
少し話題はズレますが、独立した方は安易に他人を信用しないようにしましょう。
自分を利用しようとする人ばかりなのが現実ですので、一歩間違えれば無責任な奴らにあっと言う間に食い物にされます。
自分の味方は自分だけということを肝に銘じましょう。