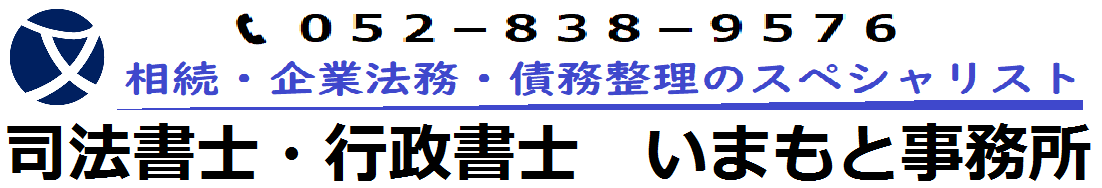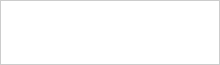株式会社をたたむ、終わらせる際には、一般的に「解散」と「清算結了」の登記が必要です。
どのように行うのか解説いたします。
スケジュール
- 解散をする
- 解散登記の申請と公告を行う
- 「知れている債権者」への催告を行う
- 公告および催告後2か月以上の経過を待つ
- 清算結了の決議をする
- 清算結了登記を申請する
おおよそこのような流れとなります。
1.解散をする
株式会社の解散事由は会社法第471条に記載されています。
合併や破産、解散命令を除き、通常は「株主総会の決議」「定款で定めた事由または存続期間の満了」を原因として解散します。
定款で「解散事由」や「存続期間」を定める会社はほとんど無いため、「株主総会の決議」により解散するのがほとんどです。
基本的に会社をたたみたい時は株主の賛成によって解散を行うと良いでしょう。
休眠会社のみなし解散
株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの、すなわち「休眠会社」は所定の手続を経て「解散されたものとみなす」ことがあります。
登記を怠って放置を続けると「みなし解散」とされ、解散の登記を職権でされることがあるので注意しましょう。
この「12年」という期間ですが、株式会社の登記は何ら定款変更等を行わずとも役員の任期が最長10年であり、その更新の登記が必要なため、12年も放置されているものは登記が必要であるにもかかわらず動いていないと判断されるためと思われます。
なお、特例有限会社は役員の任期の設定をしなくても良いのでこのみなし解散の規定は存在しません。
2.解散の登記申請と公告
(1)解散(及び清算人)の登記申請
解散の登記申請と併せて「清算人」の登記を申請します。
株式会社が解散すると、その取締役及び代表取締役は退任し、代わりに「清算人」「代表清算人」が会社の清算を執り行います。
清算人は原則として「取締役」「株主総会の決議で選任した者」「定款で定める者」が就任しますが、定款であらかじめ清算人を選任する会社は稀なので、通常は取締役がそのまま清算人となるか、株式会社によって選任することになります。
なお、登録免許税として解散登記分で3万円、清算人登記分で9000円の課税があります。
(2)公告
株式会社は解散後に「官報」という紙面に、その解散の事実を公告し、一般に公開する必要があります。
最低限の掲載費用としてはおおよそ4万円前後が見込まれ、この公告期間は2か月以上必要です。
この公告は法律上の義務であり、100万円以下の過料の対象となります。
公告の趣旨として大きなポイントは、会社に対して債権を持っている方々にその回収を促すことにあります。
3.「知れている債権者」への催告
公告に加えて、会社として知っている債権者には個別で催告を行って、基本的には残債務の支払いをします。
会社の清算は債務が無い状態まで進める必要があるので、普通に清算行為をする場合はこの通過点は当然に経ることとなります。
4.公告および催告後2か月以上の経過を待つ
公告と催告の後は2か月以上経過しないと清算を終えることができません。
この間に会社は清算業務として資産の売却や債権の回収、負債の支払いを進めることとなります。
そもそも清算というのは、おおざっぱに言えば財産と負債を整理して残った金銭を株主に分配するのが通常です。
完了する際には見落とした資産などが無いように注意しましょう。
5.清算結了の決議をする
株主総会にて清算の結果を報告し、残りの財産を株主に分配します。
それに伴い株主総会の決議を経ます。
6.清算結了登記の申請をする
晴れて会社の登記を閉鎖する「清算結了」の登記を申請します。
登録免許税として2000円の課税があります。
設立に比べての清算結了
ネット上には「会社設立のやり方」などがあふれており、自分で設立する方も少なくありません。
しかし、今一度考えましょう。
設立した後はいずれ解散と清算が待っています。
無責任に設立の方法を解説する方がこの出口について何も知らない、そんな可能性が大いにあります。
勢いで設立した会社をたたみたい、そんな時に「こんなはずでは」などと後悔しないように注意しましょう。

現実では山林などを保有したまま「みなし解散」され、期間の経過とともに登記が閉鎖されている会社が沢山あります。
このような会社が多いため、所有者不明土地問題の原因のひとつとなっています。
社会問題を生まないためにも、法律上の義務を全うするためにも、実際の会社のたたみ方は今後多くの方に知って欲しい事実です。