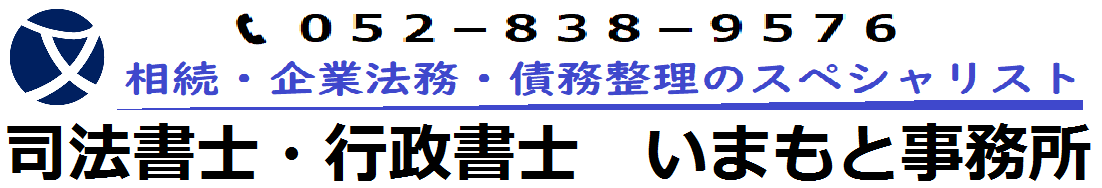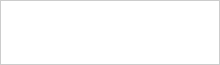マイホームを購入するとき、その登記の見積もりや領収書を見て「高いなあ」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
例えば、登記費用35万円・・・。
確かにたかだか名義を登録するのにこれは高く感じます。
この内訳は果たしてどうなっているのでしょうか?
費用の内訳
登記費用は主に報酬と実費に分かれています。
報酬も事務所によって内訳が異なりますが、
- 登記申請手数料
- 添付書類作成代
- 添付書類取得手数料
- 立会手数料
- 出張費
- 交通費
などが記載されております。
なお、弊所は比較的内訳が少なめなシンプルな書き方をしている気がします。
次に実費ですが、
- 登録免許税(印紙代)
- 添付書類取得実費
- 郵送費
- 交通費
などがあります。
この実費で最も費用に影響するのは「登録免許税」です。
登録免許税とは
登記を申請するのには登録免許税を納付する必要があります。
会社設立でも不動産登記でもそれは変わりません。
紙での申請であれば収入印紙で、オンラインの申請では電子納付も可能です。
その金額が登記費用に大きな影響を与えます。
例えば、株式会社を設立するのに最低でも15万円の登録免許税を納付する必要があります。
ご自身で申請しても15万円は免れません。
本店を移転する場合、個人で言えば住民票の転居届のレベルのことですが、それだけでも3万円(管轄外への移転であれば2申請の合計で6万円)もの登録免許税が必要です。
それでは不動産ではどうでしょうか。
所有権に関する移転や保存登記は基本的に「不動産評価」に基づく課税標準額に税率を乗ずることで算出します。
例えば土地に関し、評価額2000万円の場合は次の通りです。
※令和7年8月18日時点
- 所有権移転(売買)・・30万円(1.5%)
- 所有権移転(贈与や財産分与など)・・40万円(2%)
- 所有権移転(相続)・・8万円(0.4%)
このように、何の名目で移転するかによって税率が異なります。
贈与や財産分与の場合は高く、相続であれば低い税率となります。
なお、相続する土地の評価額が100万円以下の場合は非課税となります。
ほか、墳墓地に関する登記など非課税対象となるケースは他にもあります。
次に、例えば評価額1000万円の建物の場合は次の通りです。
- 所有権保存(減税適用あり・一般的な建物)・・1万5000円(0.15%)
- 所有権保存(減税適用あり(長期優良住宅など))・・1万円(0.1%)
- 所有権保存(減税適用なし)・・4万円(0.4%)
- 所有権移転(減税適用あり・一般的な建物)・・3万円(0.3%)
- 所有権移転(減税適用なし)・・20万円(2%)
このように、建物についてはその取得が減税の適用があるかどうかが大きな要素となります。
基本的に新築住宅は減税適用されるケースばかりですが、一定以上に古い建物や法人による購入、床面積が規定外の建物になるなど減税対象外となれば一気に税額が上がります。
しかし、例えば生前贈与などであればこのような減税対象外とはなりますが、あまりにも古すぎる建物故に評価額自体が低く結局安くなるというケースもしばしばあります。
次に、住宅購入のための抵当権ではどうでしょうか。
抵当権は債権額、借入額に税率を乗じます。
例えば借入額4000万円ではどうでしょうか。
- 抵当権設定(減税適用あり)・・4万円(0.1%)
- 抵当権設定(減税適用なし)・・16万円(0.4%)
抵当権においても減税があるかどうかが大きな要素です。
それでは上記の例で住宅購入の登録免許税をシミュレートしてみましょう。
減税あり・新築
所有権移転(土地)・・30万円
所有権保存(建物)・・1万5000円
抵当権設定・・4万円
【合計35万5000円】
減税なし
所有権移転(土地)・・30万円
所有権移転(建物)・・20万円
抵当権設定・・16万円
【合計56万円】
このように登録免許税は減税の適用があるか、その評価額や借入額がいくらかで大きく異なります。
仮に登記の報酬が数万円でも、この税金によって費用が数十万円に跳ね上がるので「高いなあ」という感想が出てしまうのです。
なお、ここで言う「減税」とは、租税特別措置法による減税を意味します。
期限のある法律ですので、その点は注意しましょう。
評価額や借入額が関係ないケース
- 住所変更登記
- 抵当権抹消登記
このような登記は不動産の個数×1000円しかかからず、安価で登記申請ができます。
したがって、ローン完済での抵当権抹消登記などはトータル費用が安いです。
住宅購入による登記費用とは天と地の差です。