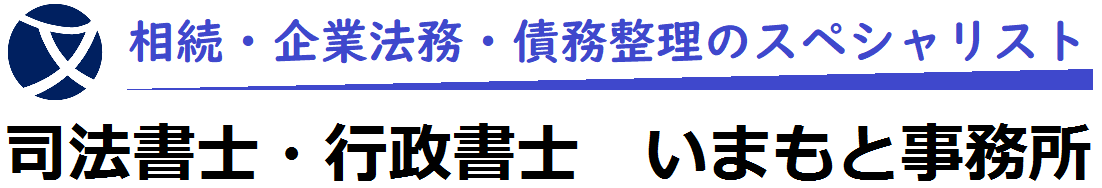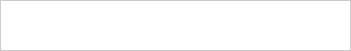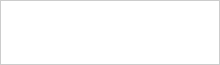相続は一生のうちに数えるくらいしか遭遇しません。
初めての方がほとんどで、人によっては全く経験することもないケースもあります。
みんな相続未経験者、だからこそ知って欲しい相続とは何か?
そして相続では何をすればいいか?
そもそも相続とは?
相続とは、人が亡くなった後にその財産などを引き継ぐこと、それは大体の方はふんわりイメージしていらっしゃると思います。
相続される財産は金銭や預貯金、不動産のようなわかりやすい財産のほか、住宅を借りる権利、いわゆる「賃借権」も含みますが、その人の全ての権利が対象ではありません。
次のような例外もあります。
【引き継がない権利の例】
- 年金や生活保護の受給権
- 会社員や会社役員としての地位
- 仏壇仏具やお墓
年金や会社員の地位はイメージが湧くと思いますが、お墓について「おや?おかしいぞ、お墓は継ぐじゃないか?」と思われる方が多いと思います。
これは民法の規定では「慣習」や「被相続人(亡くなった方)の指定」によって継ぐ者が決まるのであって、法律で相続人が厳格に定められている訳ではありません。
亡くなった方の奥様やお子様が墓を管理されているものの多くは法律による相続ではなく家の慣習によるものなんです。
なお、生命保険の受取は原則として相続財産ではなく、あくまで契約上の権利となります。
【財産だけではなく負債も引き継ぐ】
財産だけ引き継ぐという都合の良いものではなく、借金などの負債、債務も相続されます。
例えば、住宅を借りる権利を引き継ぐのであれば家賃を支払う義務も引き継がれる訳です。
「そんなのは嫌だ!どうすれば?」とお考えの方は次の項目が対策となります。
相続放棄とは?
相続放棄とは?
これを正確に答えられる一般の方はそこまで多くはありません。
これは「財産」「負債」ともに相続せず、「初めから相続人でなかった」のように扱われるための手続です。
【遺産放棄?相続放棄?】
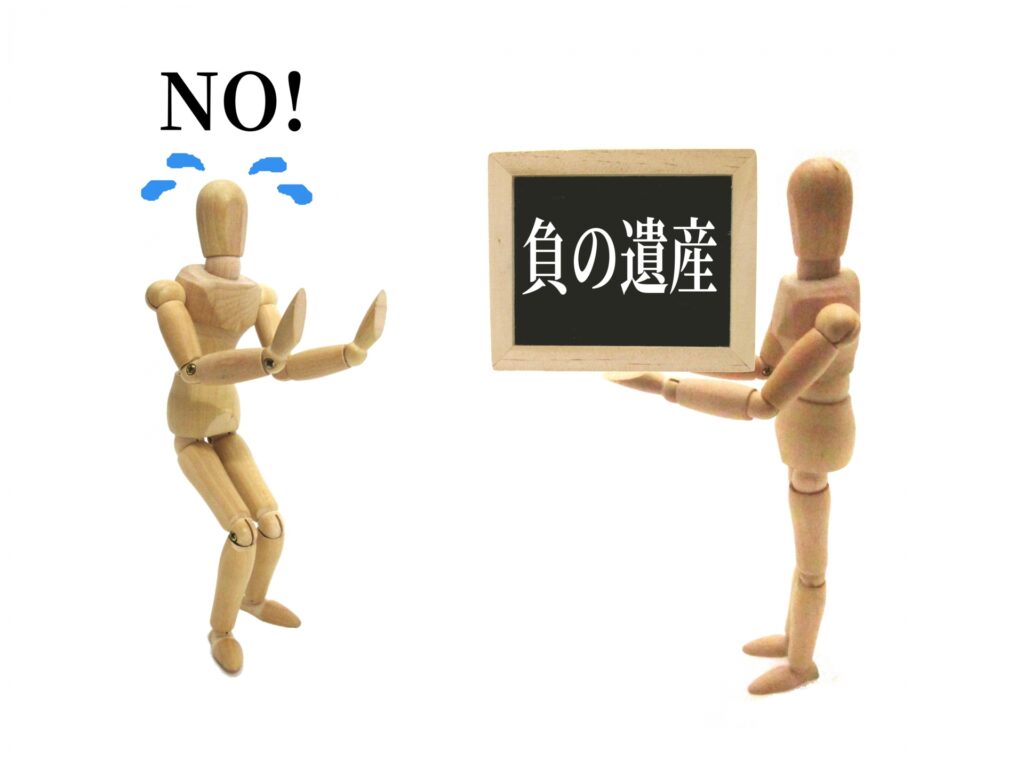
「財産いらないから勝手にそっちでやってくれ」と親族に言い放つ、書面に書くだけの行為は法律上の相続放棄ではなく、負債は免れません。
相続放棄とは、「相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に「裁判所で行う」手続のことであって、例え「私は財産はいりませんし借金も負いたくありません」と契約書や遺産分割協議書に書いたとしてもそれは相続放棄とはならないのです。
負債を免れたい方は、このような事実を誤認したまま知らず知らずのうちに3か月が経過してしまうかもしれないので、注意しなくてはなりません。
相続はまず何から始めればいいの?
次の順番で相続財産を継ぐ者を決め、手続を行います。
- 法定相続人を確定する
- 相続放棄する人や遺言書がいないか確認する
- 遺産分割協議をする
- 相続手続を実行する
この4つの手順を進めます。
【1.法定相続人を確定する】
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本を取得して法定相続人を確定させます。
法定相続人とは、相続放棄の有無について関係なく、民法上で定められた相続人のことです。
第一順位は子ども、第二順位は親などの直系尊属(祖父母含みます)、第三順位は兄弟姉妹です。
戸籍については種類が多くて戸惑う方がいらっしゃるかも知れません。
戸籍は時代とともにフォーマットが変わっており、簡単に言えば変わる前のものが「改製原戸籍謄本」であり、現行制度のものが「戸籍謄本」となります。
なお、「謄本」と「抄本」の違いは、「謄本」が全部を写したものであるのに対し、「抄本」は一部抜粋で記載されているものとなります。
「除籍謄本」は、原因あって「除かれた戸籍」となります。
例えば、「転籍」で違う本籍地に戸籍が移転した場合は、旧所在地のものが「除籍」となります。
戸籍に記載されている方全員が亡くなったり婚姻等で別の籍に入籍した場合も、もぬけの殻の戸籍は「除籍」となります。
このような書類から法定相続人を確定させます。
【2.相続放棄をする人や遺言書ないか確認する】
これはそのままの意味で、裁判所の手続で相続放棄をした人がいないか確認します。
相続放棄をした人は相続人でなかったものとして扱います。
有効な遺言書があった場合は遺言書に従う形であれば次の項目の遺産分割協議は不要です。
なお、遺言書に記載のない部分について遺産分割協議を行う事は可能であり、遺言書に反する遺産分割協議も全員の同意などの一定の要件を満たせばこれも可能です。
【3.遺産分割協議をする】
相続放棄をした人を除いた「相続人全員で」遺産分割協議を行い、誰が、何を、どれだけ相続するか決めます。
無論、誰かの相続分をゼロにすることもできますし、全部誰か一人に相続させることもできます。
何もしなければ観念上は財産が共有状態であり、そのままだと不便極まりないので遺産分割協議を行います。
例えば、亡くなった方の子どもが実家に住まないなら共有でも家なんて相続したくもなく、それよりも「預貯金や現金くれよ」と思うのは自然です。
誰も実家に住まないのなら売却して代金を分配できますが、相続人の中で誰か住む人がいるのならそれもできません。
結果的には遺産分割協議を証明する「遺産分割協議書」を作成しますが、その押印は実印が望ましいです。何故なら、次の項目でも触れますが第三者に提示する場合に実印押印と印鑑証明を求められることが多いからです。
なお、遺産分割協議を放置した場合は相続人自身が亡くなるなどして遺産分割協議の対象者がねずみ算式に増え、最悪は見ず知らずの人と手紙でやり取りする羽目になるなどロクなことになりません。
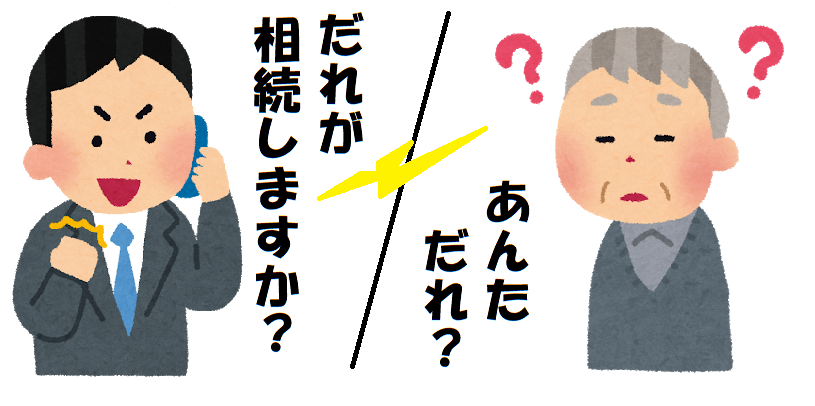
※ 遺言書があった場合は遺言書に従い分配するのが通常です。
【4.相続手続を実行する】
遺産分割協議に基づいて形見分けご親族内での相続手続は終わっているようなものですが、第三者にとっては何も起きていません。
そういった意味で、一例ですが下記の手続を行います。
- 預貯金の相続手続・・・金融機関に対して
- 不動産の相続登記・・・法務局に対して
- 相続税の申告・・・税務署に対して
(金融機関での手続)
金融機関は亡くなったことを知りません。
亡くなったことを知らせると基本的には預貯金が凍結され、相続手続待ちの状態になります。
その後に所定の書類とともに遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)や印鑑証明書、戸籍類の提出を行って相続となります。
この場合、「預貯金口座の名義変更」をするか「預貯金を解約して相続人の口座に振り込む」かの二択になるのが通常です。
(法務局での相続登記手続)
これも所定の書類とともに遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)や印鑑証明書、戸籍類の提出を行います。
登録免許税という税金がかかるので、その分の収入印紙も用意しましょう。
財産価格に応じての課税になるので、少ない人は非課税ですが、地価の高いエリアで土地建物を沢山持っている人だと数百万円に及ぶこともあります。
弊所のある名古屋市天白区では、新しめの居住用土地建物のワンセットであれば十数万円のケースが多いです。
(税務署での手続)
相続登記も3年の期限がありますが、こちらは10か月以内ともっと短いです。
控除内でおさまる財産価格であれば申告は不要ですが、算定方法等は国税庁のウェブサイトもしくは税理士の先生などにお尋ねください。
弊所でも税理士の先生のご紹介、連携は可能です。